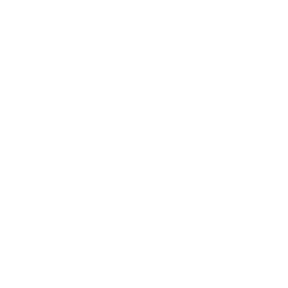日本鱗翅学会会員・指針と心得[1992年4月8日制定「やどりが」150号所載]
行動目標4カ条
- 1) 私たちは蝶蛾に親しみ, 自然を深く理解することにつとめる。
- 2) 蝶蛾とその生息環境の保護活動を積極的に進める。
- 3) 採集活動は節度をもって行なう。
- 4) 活動成果を公表し, 標本をたいせつに保存する。
総論
- 1) 私たちは蝶蛾に親しみ, 鱗翅学の発展・普及とともに自然を深く理解することにつとめる。
- 2) 蝶蛾は生態系における第1次消費者として本来大きな繁殖力をもち, 自然界ではより高次の消費者である哺乳類や鳥類に比べて著しく個体数が多い。また体が小型で外観の似た種が多いため, 野外観察だけでは種の同定が難しく, その研究には採集して標本を製作することが必要となる。したがって採集によらない識別記録方法が優先される哺乳類や鳥類の場合とは研究方法が異なる。
- 3) 蝶蛾は環境指標としてすぐれており, それらの正確な採集・観察記録は環境保護のための基礎的データとしての価値が高い。一般に蝶蛾の豊富な環境は多様性に富み, 他の生物の生存にとっても有利となる。私たちは日本の蝶蛾の繁栄のため, それらの生息地の植生や自然環境を守らなければならない。その目的を遂行するため,必要に応じて環境行政やマスコミに働きかける。
- 4) 健全な節度のある採集活動, とくに児童・生徒による採集活動は, 観察活動に劣らず貴重な自然体験としての意味があり, 正しい自然観を養う上できわめて重要である。一部で提唱されている, ただ「採らずに観察しよう」という考え方には, 子どもたちから積極性を奪い, かえって彼らを自然から遠ざけてしまうおそれがある。
- 5) 私たちは地域や時期を定めない「種指定」の採集規制には原則的に反対する。それはその種の保護に役立たないばかりでなく良心的なナチュラリストの野外活動を大幅に制限することになり, 日本の鱗翅学研究の発展を著しく阻害するからである。採集規制の方法に問題があるときには, 会として行政当局に対し, 積極的に意見を申し入れる。
- 6) 私たちは, とくに産地の異なった蝶蛾をみだりに野外に放す「放蝶」には賛成できない。ただし, 周到な計画と事後の責任を伴った保護活動または研究を目的としたものはこの限りではない。
- 7) 採集された標本はかけがえのない学術資料であり, その保存には細心の注意が必要である。このような資料を保存するための自然史系博物館の事業に協力し, またその新設を積極的に支援する。
諸活動上の留意事項
- 1) 採集や観察にさいしては, 生息地の環境を損なわないように気をつける。
- 2) 採集のさいには個体群の維持に配慮し, 採集個体数を自主的に制限する。とくに狭く限られた産地ではこのことに留意する。
- 3) 採集・観察地において, 土地の所有者, 管理者, そのほか地域の人たちの理解が得られるようにつとめる。
- 4) 法律によって採集が規制されている地域ではその法律にしたがう。
- 5) 海外では, それぞれの国の法律や国民感情を十分に理解し, 国際人としてはずかしくない行動をする。
- 6) 標本はたいせつに責任をもって保管する。とくにタイプ標本はなるべく適当な博物館など, 信用のおける公共機関に保存されることが望ましい。また, さまざまな事情により標本の保管が不可能になった場合は, 適当な研究者または公共機関などに寄贈するように心がける。
- 7) 採集活動などによって得られた成果はできるだけ速やかに公表する。