日本鱗翅学会版「保全のシンボルとしての都道府県のチョウ」が決定されました!
2025年2月19日公開
2019年から、日本鱗翅学会自然保護委員会により「保全のシンボルとしての都道府県のチョウ」の選定企画が始まりましたが、2024年6月に会員投票が行われ、ついに決定されました。各都道府県のチョウとその選定理由は、以下のPDFに概説していますので、ご覧ください。
- 日本鱗翅学会版「保全のシンボルとしての都道府県のチョウ」の決定|やどりが283号 P41-45 (PDF/892KB)
モンキチョウ Colias erate poliographus
(シロチョウ科モンキチョウ亜科)
モンキチョウは平地から亜高山帯まで、日本各地に広く分布する普通種である。早春から晩秋にかけて、公園や堤防などの開けた環境を活発に飛び回る成虫の姿がしばしば見られるが、いざ採集しようとすると意外に素早く、子どもが持つ網ではなかなか捕らえられない。
観察を続けていると、写真のように雌雄が並んでホバリングする場面に出会うことがある。モンキチョウの♂は常に黄色で、♀には黄色型と白色型が存在するため、写真では左が♀、右が♂である。多くの蝶類と同様に、モンキチョウでも♂は♀を求めて飛び回り、発見すると一目散に追尾する。野外で見られる♀の多くはすでに交尾を済ませており、そのため♂の求愛行動は大半が失敗に終わるが、♀が即座に拒否行動を示さない場合には、このような空中での追尾がしばらく継続することがある。
このとき、雌雄の位置関係をよく観察すると興味深い点に気づく。追尾しているはずの♂が、実際には♀の前方を飛んでいるのである。これは、♂の翅表(種によって分泌器官の位置は異なる)から揮発性の化学物質が放出されており、それが性フェロモン(同種の個体間で交信を行うために用いられる化学物質)として作用し、♀にその香りを嗅がせているためと考えられている。
チョウの性フェロモンに関する研究は、ガに比べて進展が遅れており、その機能は未解明な点が多いが、どうやら♀の警戒心を和らげ、♂の求愛を受け入れやすくする役割があるとされている。
2025年2月19日公開
2019年から、日本鱗翅学会自然保護委員会により「保全のシンボルとしての都道府県のチョウ」の選定企画が始まりましたが、2024年6月に会員投票が行われ、ついに決定されました。各都道府県のチョウとその選定理由は、以下のPDFに概説していますので、ご覧ください。
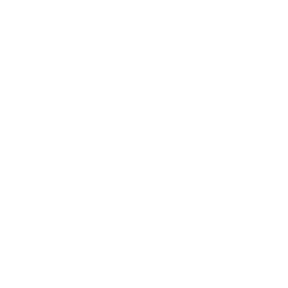
鱗翅(りんし)というのは鱗翅目(チョウ目)Lepidopteraのことで、鱗粉のある翅を持った昆虫すなわちチョウやガの仲間です。この小さな生き物はその素晴しい魅力で古い時代から私たちをひきつけてきました。日本鱗翅学会はこのチョウやガを研究対象とする学術団体で、アマチュアから専門家まで幅広い層のメンバーが協力しながら活動しており、興味のある人は誰でも入会できる開かれた学会です。