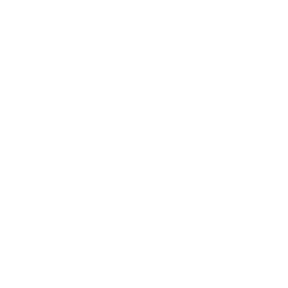第54回日本鱗翅学会大会のご案内
2007年10月27日公開
日本鱗翅学会第54回大会は信越支部が担当し、新潟市で開催されることとなりましたのでご案内申し上げます。 新潟市は平成19年4月1日より本州日本海側初の政令指定都市となりました。市民一同心から歓迎いたしますので、是非お出かけください。
1.会場
- 大会・総会
- 新潟大学医学部有壬(ゆうじん)記念館
新潟市中央区旭町通1-757
Tel:025-227-2037 - 懇親会
- ホテルディアモント新潟
新潟市中央区本町通6-1099
Tel:025-223-1122 - 会場地図はこちらをクリック
- 2007年10月27日(土)
- 特別講演、一般講演、小集会、ポスター発表、懇親会
- 2007年10月28日(日)
- 一般講演、総会、ポスター発表(コアタイム)、小集会、シンポジウム
- 宿泊
- 宿泊の斡旋は致しません。以下にいくつかのホテルを紹介しておきましたが、各自でお早めに確保してください。 なお、大会会場への車の乗り入れはできません。
- 会場へのバス路線の案内
- JR新潟駅万代口より下記系統の新潟交通バスで「市役所前」下車、徒歩5分。 系統7番 県庁前行き。 系統11番 西部営業所行き。 系統11A番 信濃町先回り新潟駅行き。
- 大会会長
- 樋熊清治
- 大会副会長
- 佐藤力夫
- 事務局長
- 櫻井 精
- 新潟東急イン(1分)
- 025-243-0109 6,825円から
- 東横イン新潟駅前(1分)
- 025-241-10456,090円から
- ニイガタステーションホテル(1分)
- 025-243-51515,250円から
- 新潟第一ホテル(1分)
- 025-243-11115,775円から
- 新潟東映ホテル(5分)
- 025-244-71018,085円から
- ホテルディアモント新潟(懇親会場)
- (新潟駅から徒歩15分) 025-223-11227,800円から
- カントリーホテル新潟(懇親会場の隣、新潟駅から徒歩15分)
- 025-229-33005,500円から
- 新潟シティホテル新館(新潟駅から車で8分)
- 025-224-41217,450円から
- 12:00
- 受付開始
- 13:00-13:15
- 大会会長挨拶、会長挨拶、事務連絡
- 13:15-14:30
- 特別講演 平賀壯太「蝶のサナギの謎-昆虫研究の勧め 」(一般公開)
- 15:00-16:00
- 一般講演(101から104)
- 15:00-15:15
- 101.台湾産「キチョウ」2型の季節型反応と寄主選好性/○加藤義臣(関東)・矢田 脩(九州)・Yu-Feng Hsu(台湾)
- 15:15-15:30
- 102.鳥類の巣から発見される鱗翅類/那須義次(近畿)
- 15:30-15:45
- 103.長野県南部での照葉樹林性キリガの分布について/四方圭一郎(信越)
- 15:45-16:00
- 104.M. A. Fentonの来日目的と大英博物館/○中村和夫(関東)・松田真平(近畿)
- 16:10-17:40
- 小集会 新潟県におけるオオルリシジミの保全に向けて 企画者:中村康弘・矢後勝也(関東) アゲハモドキ研究会 企画者:中臣謙太郎(関東)
- 18:30-20:30
- 懇親会・ホテルディアモント新潟
- 8:50- 9:00
- 開会,事務連絡
- 9:00-11:30
- 一般講演(201から210)
- 9:00- 9:15
- 201.柏崎西山町ゆうぎのバタフライガーデンと夢の森公園/佐藤俊男(信越)
- 9:15- 9:30
- 202.阿賀野川流域のウスバシロチョウにみられる「地形効果」について/樋熊清治(信越)
- 9:30- 9:45
- 203.ウスバシロチョウ黒化標準モデルについて/○小野克己(近畿)・寺 章夫(関東)
- 9:45-10:00
- 204.モンゴル・ハルヒラー山の蝶類/○大島良美・中谷貴壽(関東)
- 10:00-10:15
- 205.フタスジコスカシバの生態/福住和也(東海)
- 10:15-10:30
- 206.海岸および河口付近に生息するメイガ類(Pyraloidea)の生態/吉安 裕(近畿)
- 10:30-10:45
- 207.Acer属の中でカジカエデ1種に固有な蛾類2種,ハネブサシャチホコとノコバフサヤガ/中臣謙太郎(関東)
- 10:45-11:00
- 208.絶滅危惧種ミヤマシジミの保全に関する基礎的研究 4.アリ類との共生関係における種・地域による共通性と相違/ ○渡辺通人(関東)・大村 尚・本田計一(中国)
- 11:00-11:15
- 209.スジグロシロチョウとエゾスジグロシロチョウの香気物質の比較/○棚橋一郎・榎本将典(近畿)
- 11:15-11:30
- 210.ツマキチョウにおいて重複産卵は致命的か?/稲森啓太(近畿)
- 11:30-12:00
- ポスター発表コアタイム
- 12:00-13:00
- 自然保護委員会
- 13:00-13:30
- 日本鱗翅学会総会
- 13:40-15:10
- 小集会 ロシア沿海地方の鱗翅類 I 企画者:宇野 彰(関東)・四方圭一郎(信越) 日本鱗翅学会アサギマダラプロジェクト公開シンポジウム 企画者:渡りチョウを調べる会(旧アサギマダラプロジェクト)平井規央・石井 実・藤井 恒(近畿)
- 15:15-16:45
- シンポジウム 「DNAにみる進化の道筋と"種"」 コーディネーター 八木孝司(近畿) 「キチョウEurema hecabe」の種分化とDNA解析/加藤義臣(関東) 日本列島産ベニヒカゲの系統地理/中谷貴壽(関東) DNAに基づく同定技術「DNAバーコーディング」と鱗翅目研究への活用/○神保宇嗣(関東)・伊藤元己(東大) シルビアシジミ属の分類と系統生物地理/ ○矢後勝也(関東)・平井規央(近畿)・近藤真理子(東大)・谷川哲朗・石井 実(近畿)・王 敏(華南農業大学)・Mark Williams(プレトリア大学)・上島 励(東大)
- 16:45-16:50
- 閉会
- P-1
- 東京都足立区におけるツマグロヒョウモンの増加と越冬/瀬田和明(関東)
- P-2
- 蛾類幼虫百態(7)コウチスズメの生活史・ツバキ科落葉樹Stewartia属に固有な蛾類/中臣謙太郎・横田光邦(関東)
- P-3
- 富士山北西麓青木ケ原樹海周辺におけるチョウ類の多様性と蜜源植物種数の関係/北原正彦(関東)
- P-4
- 蝶による環境指標と地域特性との相関/松井安俊(関東)
2.日程
3.参加申し込み
当日、会場にて参加費をお支払い下さい。会員は「やどりが」の振込用紙に必要事項をご記入のうえ、大至急送金してください。
4。会費
大会参加費2,000円 懇親会費8,000円
5.宿泊・交通
6.大会事務局
この大会に関するすべてのお問い合わせは、佐藤力夫までお願いします。 メールアドレス:lsj54-niigata@g-sigma.co.jp
7.その他
28日(日)の昼食(弁当)の斡旋を致します。会場受付にてお申し込みください。 館内は喫煙・飲食が禁止されています。また駐車スペースはありません。
※ホテルのご案内
新潟駅周辺にはこの他にも多数のホテルがありますので、各自でご予約ください。 参考までにいくつか紹介いたしますが、価格は概略ですので、予約されるときに電話などで確認してください。
新潟駅周辺
()内は駅から徒歩での所要時間
懇親会場のホテルとその周辺
大会プログラム
*プログラムは9月当初時点のものです。一部変更する場合もありますのでご承知おき下さい。